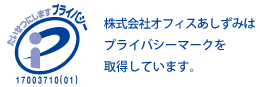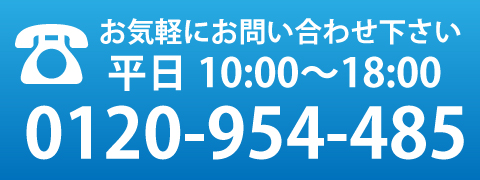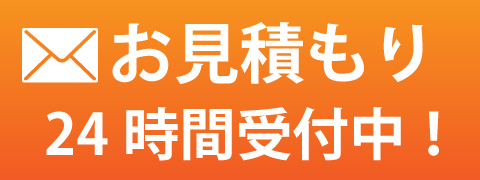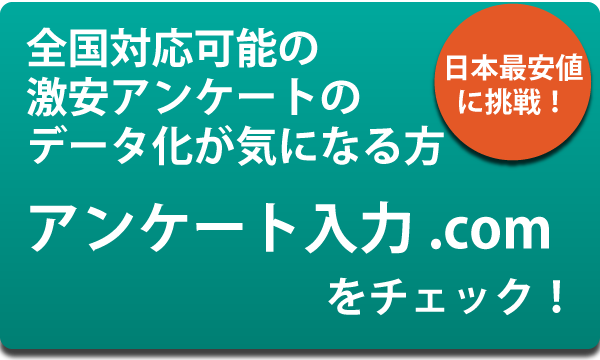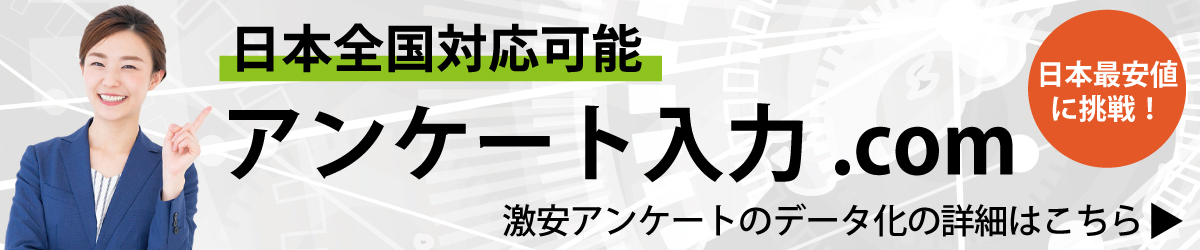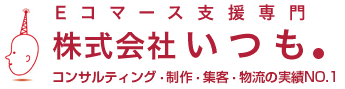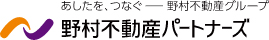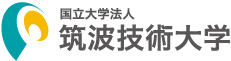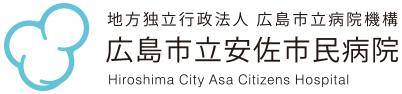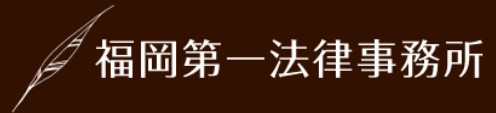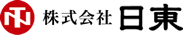目次
『相関関係』と『因果関係』
アンケートなどの市場調査では様々なデータを集めてその関連性を探すところから分析は始まります。そこで注意したいポイントが『相関』と『因果』の違いです。 『因果』とは、異なる事象が原因と結果としてつながっていること。『風が吹けば桶屋が儲かる』は風が吹いたことによって桶屋が儲かっているので、因果関係があることになります。 では相関関係とはどのようなものなのでしょうか。相関関係とは「一方の値の大きさと、もう一方の値の大きさに関連性がある」関係のこと。 例えば「Aが多いとき、Bも多い傾向がある」という場合、AとBは相関関係があると言います。 では相関関係について具体的な例を見てみましょう。交番の数が多い程、犯罪件数が多い。
地域に交番が多いと、それだけ犯罪への抑止力となるので犯罪件数は少なくなるように思われます。しかし現実には交番の数に比例して犯罪件数が高い地域もあります。 ではそういう地域では、交番を減らしたら犯罪発生率は減るのでしょうか。実際そう上手くはいきません。こういう地域ではもともと犯罪発生率が高いから、治安を守る為に重点的に交番が設置されているのです。もしも犯罪抑止のための交番を減らしてしまったら、逆に犯罪発生率は高くなってしまいます。「交番が多いから犯罪発生率が高い」のではなく「犯罪発生率が高いから交番がたくさん必要になった」のです。 「交番が多い」と「犯罪件数が多い」は相関関係はあるけれど、『因果関係』はないことがわかります。 しかし、「犯罪件数が多い」から「交番が多い」は成り立ちます。このように因果関係は原因と結果を取り違えると成り立たないものが多いです。
最後に
アンケートなどで集まったデータを分析する際、いろいろな数字を比較して傾向や法則を見つけ出そうとするわけですが、連動する二つの要素を見つけたからといって早々に因果関係があると決め付けるのではなく、一度冷静になって- ただの偶然かもしれない
- 因→果が逆かもしれない
- 実は二つの要素にはそれを変動させている共通の原因があるかもしれない