大学での現役学生や卒業生のアンケートが増加する2025年度、限られた職員体制で正確かつ迅速な入力業務には外注という選択肢
学生や卒業生アンケートが大学で急増する背景とは?
2025年度に入り、全国の大学では学生および卒業生を対象としたアンケートの実施件数が顕著に増加しています。これは単なる一過性の現象ではなく、大学を取り巻く社会的・制度的な要請の変化、そして教育の質保証への取り組み強化といった複合的な要因によって起きているものです。
まず第一に挙げられるのが、文部科学省による内部質保証(IR:Institutional Research)強化の流れです。近年、各大学における教育・研究・学生支援の質の可視化が強く求められており、その基盤となるのが、学生本人や卒業生からのフィードバックです。たとえば、
-
授業満足度アンケート
-
卒業後の就職・進路状況調査
-
キャリア支援サービスに対する意識調査
-
FD(Faculty Development)関連の教育改善アンケート
などが、学期ごとや年度末ごとに実施される傾向が強まっています。こうしたアンケートは、各学部や研究科、キャリアセンター、教務課、IR室など、大学内の複数部門で並行して行われるため、年々対象数と件数が増加する一方となっています。
また、大学が第三者評価機関(大学基準協会、認証評価機関等)への提出資料として、アンケート結果のエビデンスを求められる機会が増えていることも、アンケート実施の頻度を高める要因となっています。これにより、単なる内部報告にとどまらず、外部に対して説明責任を果たす資料としての精度・網羅性が求められるようになりました。
次に、社会的背景としての少子化と高等教育の競争激化があります。大学間での学生募集競争が厳しさを増す中、学生の満足度、就職支援の実効性、キャンパスライフの充実度などを定期的に把握し、改善につなげる取り組みが大学経営に直結するようになってきました。これは、在学生・卒業生のリアルな声を「大学のブランド価値」や「教育成果」として可視化する必要があることを意味しています。
たとえば、ある大学ではオープンキャンパス参加者の満足度調査を皮切りに、入学直後の生活適応調査、授業中間調査、卒業年次のキャリア形成調査、卒業後の追跡調査と、1人の学生に対して5〜6回のアンケートが実施される体制が整備されつつあります。
こうしたアンケートの多くは、紙とWebの併用形式で実施されています。特に卒業生アンケートでは、メールやLINEによる回答依頼に加え、返信用封筒付きの紙調査票を郵送するケースも多く、回収方法が多様化しています。その分、入力業務は煩雑さと件数の両面で膨大になる傾向にあります。
加えて2025年度は、就職活動の構造変化や企業からのインターンシップ評価導入なども影響し、卒業生のキャリア形成や就業実態に関する調査ニーズが高まっている年でもあります。これにより、これまで卒業後の追跡調査を実施していなかった中堅大学や私立大学においても、調査の新規実施が進められています。
さらに、学生の多様化・国際化も、アンケート実施の複雑性を高めています。留学生や社会人学生への対応、障がい学生支援に関する意識調査など、対象の属性に応じた多言語・バリアフリー対応アンケートが必要になってきており、調査項目数や記述欄の量も増加傾向にあります。
このような背景のもと、大学が実施する学生・卒業生アンケートは「数」も「質」も飛躍的に向上している一方で、それを支える事務職員の体制は限られたままという課題があります。特に多くの大学では、教務・学生支援・広報・IRなどを兼任する職員がアンケート関連業務を担当しており、入力・集計作業に時間をかける余裕がないという現実があります。
にもかかわらず、アンケートの結果は「資料としてすぐに使える状態」に整えなければならず、短期間で大量の回答票を正確に入力するという矛盾したタスクが毎年繰り返されています。このような状況の中で、「アンケート入力業務を外部に委託する」という判断が、現場から支持されつつあるのです。
次章では、こうした大学職員の現場が実際にどのような課題に直面しているのか、アンケート入力業務が抱える負担の実態について詳しく見ていきます。
職員にのしかかるアンケート入力業務の現実
大学における学生・卒業生アンケートは、教育の質の向上や進路支援の精度向上など、組織全体の成果に直結する重要な調査です。しかし、その実施にあたって最も負担が集中するのが、アンケート回答の入力作業を担う事務職員です。
2025年度現在、多くの大学では、調査の設計から配布・回収・入力・集計・分析・報告までを、限られた職員体制の中でまかなっているのが実情です。特に国公立大学では職員数が年々減少しており、私立大学でも経費削減の影響で、事務部門に余裕を持たせる余地が少なくなっています。こうした状況の中、アンケートの件数と重要性が増していることは、職員一人ひとりの業務負担が拡大していることに直結しています。
時間と集中力を要する「地味で過酷な作業」
アンケート入力業務は、一見単純な作業のように見えるかもしれません。しかし、実際には多くの確認・注意・手間が必要な“神経をすり減らす”仕事です。
たとえば、1学部で1,000名の学生を対象に実施した紙ベースの授業満足度調査では、設問数が15問前後、うち自由記述が2~3問含まれることが一般的です。これだけでも、1件あたりの入力にかかる時間は平均2〜3分。全体で考えれば30〜50時間以上の入力作業になる計算です。
しかも、単純にキーボード入力するだけでなく、以下のような確認が都度発生します:
-
○×記入が不鮮明な設問の判断
-
途中で回答が抜けている場合の空欄処理
-
記述欄の文字判別(筆圧が薄い・読みにくい・略語や誤字)
-
不適切表現や個人名記載への配慮(伏せ字や修正要否)
これらをすべてマニュアル通りに行いながら、決められた納期内に正確に完了させるプレッシャーは大きなものです。
業務のピークと重なりやすいアンケート入力
大学業務の多くは、年度末・年度初め・学期末に集中します。新年度の履修登録対応、卒業判定、入試業務、シラバス公開、ガイダンス準備などに加えて、各学部・研究科・全学共通教育などで一斉にアンケートが実施されるため、アンケート入力業務が“他の繁忙業務と重なる時期”に発生するのが常態化しています。
特にIR部門やキャリアセンター、教学系の事務室などでは、「本来のコア業務」に時間を割けず、入力作業に追われてしまうという声が多く聞かれます。
属人化・ノウハウの断絶という別のリスク
加えて、アンケート入力作業は担当者に依存しやすい業務のひとつです。設問形式や入力ルール、自由記述の扱い方など、年度や部署によって微妙な違いがあり、それを「なんとなく前例にならって処理している」というケースも珍しくありません。
これはつまり、担当者が異動や退職をすると、過去との一貫性が失われたり、ルールの引き継ぎが不十分になるリスクを内在しているということです。とくに卒業生調査など、数年越しのデータ比較が求められる調査では、入力基準のブレは大きな問題になります。
組織的ストレスと作業品質の低下
忙しい中で大量の入力を処理しようとすれば、どうしても以下のような問題が生じます:
-
単純な入力ミス(数値誤入力、誤変換、チェックマークの転記ミス)
-
自由記述の誤読・誤解釈
-
データ形式の統一ミス(例:半角・全角の混在、記号表記ゆれ)
これらは、分析結果や報告書の信頼性を損ねる原因となるだけでなく、指摘・修正作業が後追いで発生し、さらに工数がかかるという悪循環を引き起こします。
また、入力精度を担保しようとするあまり、確認作業が何重にもなり、全体の納期遅延を招くといったケースもあります。こうなると、調査の意義自体が損なわれかねません。
現場から上がる「外注したい」という声
実際に多くの大学職員からは、「入力だけでも外注できれば、調査設計や報告分析に集中できるのに」「この作業さえなければ、授業改善につながる企画がもっと進められるのに」といった声が寄せられています。
特に2020年代以降の大学では、教育DXや学生支援の高度化が進められる中で、事務職員に求められるスキルも“考える業務”へとシフトしており、反復的な単純作業をどう減らすかが課題とされています。
アンケート入力業務は、その最たる対象のひとつであり、外部に切り出すことで職員の業務負担を軽減しつつ、作業品質も維持・向上できる領域です。
次章では、実際にアンケート入力を外注することで大学にもたらされる具体的なメリットについて、スピード・精度・コストの観点から詳しく解説していきます。
入力作業を外注することで得られる大学業務の最適化効果
大学における学生・卒業生アンケートは、教育の質保証や施策改善に欠かせない基礎データとなる一方、その入力業務には多大な労力と時間がかかることが、前章で明らかになりました。こうした状況を打開する手段として、入力作業を外部の専門業者に委託(外注)する選択肢が注目されています。
入力作業の外注は、単なる事務作業の「下請け」ではなく、大学組織全体の業務最適化とアウトプットの品質向上を実現する戦略的な施策となり得ます。ここでは、大学がアンケート入力を外注することで得られる主要なメリットを、以下の3つの視点から整理して解説します。
1.スピードの向上:施策への反映を早め、意思決定を加速
アンケートは、集めるだけでは意味がなく、集計・分析結果をいかに早く意思決定につなげられるかが非常に重要です。とくに授業改善アンケートや進路調査などは、学期末・卒業期・報告書提出期といったタイトなスケジュールの中で結果が求められるため、入力作業に時間をかける余裕がありません。
外注を活用すれば、数百〜数千件単位の回答票を、わずか数日でデジタルデータに変換することが可能です。専任の入力オペレーターがチーム体制で作業を行い、さらにダブルチェックや品質確認も並行して進められるため、内部で処理する場合の2倍〜5倍のスピード感で納品が完了します。
このようにして迅速にデータが整備されることで、教員会議や委員会での共有、広報資料への活用、教育改善の企画立案までの流れが大幅に短縮され、大学としてのPDCAサイクルを加速させることができます。
2.精度の向上:入力ミスを防ぎ、信頼性の高いデータを構築
人の手による入力には、どれだけ注意しても一定のミスが生じる可能性があります。特に大学のアンケートには、選択式の他に自由記述欄が多く含まれており、読み取りや判断が難しい記述内容をどう処理するかは重要な課題です。
入力代行業者の多くは、専門スタッフによるダブルチェック体制や、記述欄の正確な転記と分類作業の経験値を持つ入力オペレーターを配置しており、誤入力や読み違いを防ぐ体制を整えています。特に、筆圧の薄い文字、崩した文字、専門用語の読み取りなど、大学ならではの難しさにも対応可能な業者を選べば、入力精度は大きく向上します。
また、自由記述をカテゴリ別にタグ付けし、要約や分類まで対応してくれる業者も存在しており、入力だけでなく初期的な分析作業を省力化できる点もメリットです。こうしたプロの作業は、職員やアルバイトの手作業に比べて、一貫性があり、再利用性の高いデータ作成が可能となります。
3.職員の工数削減とコア業務への集中:働き方改革にもつながる効果
アンケート入力を外注することで得られるもう一つの大きな利点は、職員の時間的・精神的な余裕を生み出せることです。
多くの大学では、教務、IR、キャリアセンター、広報、総務などの部署がアンケート業務を分担していますが、入力作業は本来の職務ではなく「雑務」や「追加業務」として扱われがちです。そのため、日常業務との両立が難しく、時間外対応や休日作業につながることも少なくありません。
入力業務を専門業者に委託すれば、職員は調査設計・広報・データ分析・報告書作成など、より本質的で創造性の高い業務に専念することができます。これは大学全体としての人材活用の最適化であり、同時に「職員の働き方改革」にも貢献する取り組みと言えるでしょう。
また、担当者が異動や退職をしても、外注パートナーとの関係を維持することで業務の継続性が担保されるという効果もあります。業務が属人化せず、外部に入力仕様やルールが共有されていれば、年度をまたいでも安定した業務運用が可能です。
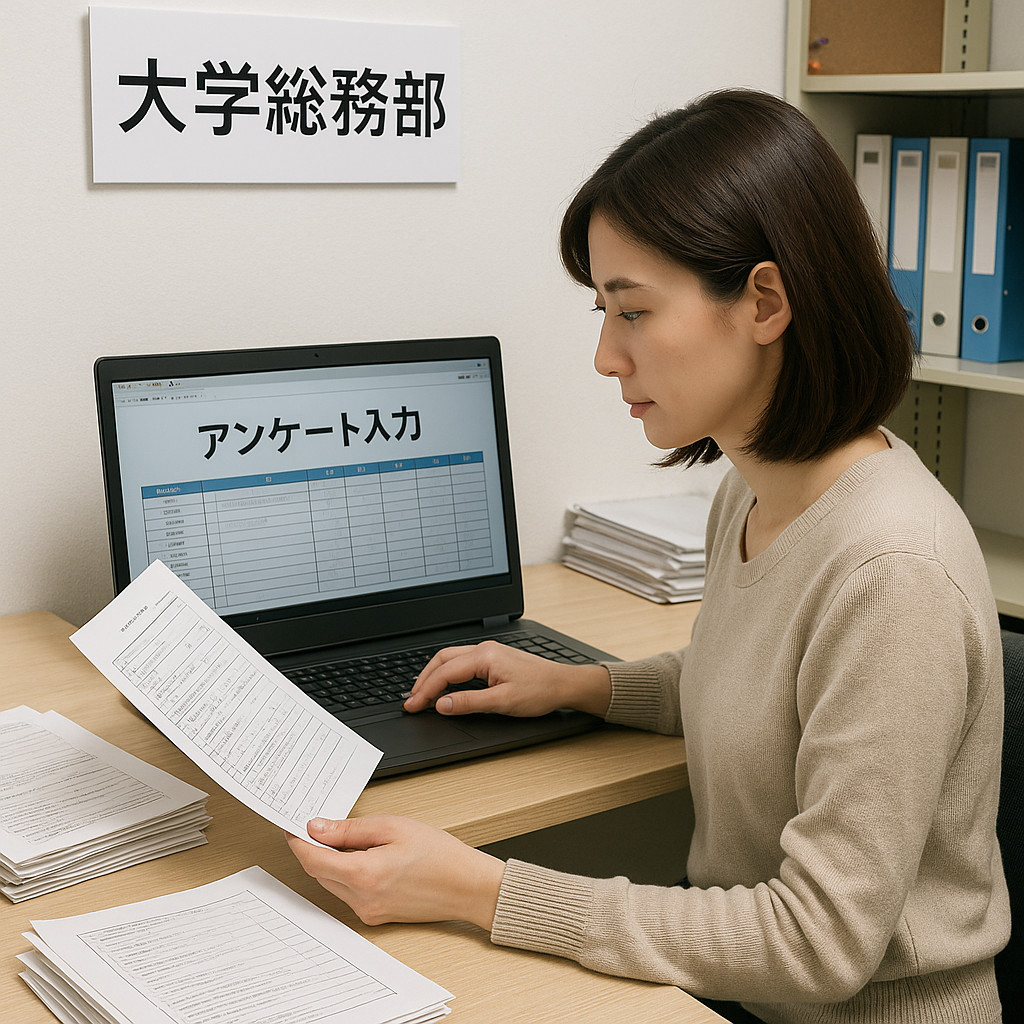
その他のメリット:費用対効果と柔軟な対応
外注の費用については、調査票1件あたり数十円から依頼できるケースが多く、件数や納期に応じて見積もりされます。内部の人件費や残業代、教育コスト、再入力による二度手間を考慮すれば、外注は十分に費用対効果が見込める選択肢です。
また、多くの業者は「Excel形式」「CSV形式」「グラフ付き報告書」「クロス集計付きデータ」など大学の希望に応じた納品形式を選択できるため、納品後の業務連携がスムーズになる点も見逃せません。
アンケート入力の外注は、大学組織の質的向上に直結する業務改革の一環です。次章では、大学が業者を選定する際に注意すべきポイントを具体的に解説していきます。
大学が入力代行業者を選ぶ際に確認すべきポイントとは
アンケート入力を外注することで、大学業務におけるさまざまな課題を解消できることはすでに述べた通りです。しかし、その効果を最大化するためには、信頼できる業者を選定することが不可欠です。費用や納期だけで判断してしまうと、入力精度の不備や納品トラブルなど、かえって手間とコストが増す結果にもなりかねません。
本章では、大学がアンケート入力業務を外注する際に、必ず確認すべき主要なポイントを5つに整理して解説します。
1.個人情報保護体制とセキュリティレベル
大学が実施するアンケートの多くには、学生番号、氏名、メールアドレス、進路状況などの個人情報が含まれる場合があります。特に卒業生アンケートや奨学金関連調査では、連絡先や就職先企業名など、センシティブな情報を扱うケースも少なくありません。
したがって、入力代行業者がどのような個人情報保護体制を整備しているかは、最も重要な選定基準となります。
確認すべきポイントは以下の通りです:
-
プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(ISO27001)認証の取得有無
-
原本保管・データ転送・廃棄方法の具体的手順
-
入力オペレーターへの教育や誓約書の整備
-
オンラインストレージ・メール送付時の暗号化対応
-
作業環境の物理的・ネットワーク的セキュリティ(入退室管理、VPNなど)
これらがしっかりしている業者であれば、万が一のリスクに対しても備えがあると判断できます。
2.自由記述欄や手書き文字への対応能力
大学のアンケートは、単純な○×や選択式だけでなく、自由記述欄のウエイトが高いことが特徴です。たとえば、
-
授業への意見・改善提案
-
キャリア支援への満足度と要望
-
教員への感謝・苦情
-
留学生の生活上の不安点
-
卒業後の進路・生活状況の詳細な記述
など、感情や背景を含んだ複雑な表現が多く含まれています。
この自由記述欄の入力は、単に読み取って打ち込むだけではなく、意味が通るように正確に転記し、適切なフォーマットで整えるスキルが求められます。特に手書きの場合は、筆跡の判読能力や経験による推測が必要になるため、業者の実務経験と対応体制が問われるポイントです。
質問事項としては:
-
読みにくい文字の判断ルールは?
-
意味不明・曖昧な記述への対応方法は?
-
差別的・不適切表現への処理ルールは?
-
類似表現のカテゴリ分類や要約処理の対応可否
などを事前に確認しておくと安心です。
3.納期対応と業務体制の柔軟性
大学のアンケート業務は、「学期末までに分析結果が必要」「報告書提出期限が迫っている」など、タイトなスケジュールを求められる場合が多々あります。したがって、依頼したボリュームに対して、どの程度の期間で納品できるのか、納期遵守率や実績がどうかも重要です。
加えて、突発的に追加依頼が発生した際、柔軟に人員を増やして対応できるかどうか、担当者の窓口が明確か、進捗報告の仕組みがあるかなど、プロジェクト管理力も業者選定において重視すべきポイントです。
4.納品形式・データ構造の対応範囲
入力されたアンケートデータは、大学内部で分析・報告・公開資料などに再利用されるため、納品形式の柔軟性と整合性も欠かせません。
以下のような対応が可能かを確認しましょう:
-
Excel/CSV形式での納品(文字コード指定含む)
-
区切り記号、セル幅、表記揺れへの配慮
-
数値・カテゴリのコーディング対応
-
グラフ・簡易集計表の作成対応(オプション)
-
クロス集計やクロスフィルター用のタグ付け対応
特にIR部門や教学マネジメントチームでは、大学独自の集計ルールやBIツール連携が求められるケースもあるため、実際の作業環境との相性も確認しておきましょう。
5.大学・教育機関への対応実績の有無
最後に重視すべきなのが、**業者の「大学業務への理解度」**です。自治体・民間企業との実績が豊富でも、大学特有の用語や運用に不慣れな業者の場合、細かなニュアンスの行き違いや手戻りが生じやすくなります。
以下のような情報を事前にヒアリングすると安心です:
-
過去の大学・短大・専門学校などへの導入実績
-
国公立・私立・規模別での対応経験
-
教育業界特有のスケジュール感(学期制、入試対応など)への理解
-
類似業務(学生調査、卒業生調査、IR支援など)の納品サンプル提示
信頼できる業者であれば、大学の目的や現場の事情を汲んだ提案ができるだけでなく、コミュニケーションもスムーズに進みやすくなります。
安さだけで選ばず、トータル品質で判断を
最後に強調したいのは、「とにかく安い業者」に依頼することが必ずしも得策ではないという点です。初期コストは安くても、納品されたデータの精度が低かったり、修正・手戻りが発生した場合、かえって時間と工数が膨らむリスクがあります。
また、セキュリティや記述対応に不備があると、学生の信頼を損ねるだけでなく、個人情報保護に関する重大な問題に発展する可能性もあるため、大学としての社会的信用にも関わる重要事項です。
次章では、実際にアンケート入力の外注を導入した大学の事例をご紹介し、外注の導入効果や進め方のイメージを具体的に掴んでいただきます。
実際に導入した大学に見るアンケート入力外注の活用事例
アンケート入力の外注は、大学における業務効率化や品質向上に寄与する手段として、全国的に導入が進んでいます。実際に導入した大学では、単なる入力作業の軽減にとどまらず、教育の質保証、学生支援、IR推進など、多方面での効果が報告されています。
この章では、入力代行を活用した大学の具体的な導入事例を3つご紹介し、外注がどのように大学業務に貢献しているのかを明らかにします。
ケース①:中規模私立大学での「卒業生追跡調査」の効率化
関東地方にある中規模私立大学では、2022年度から卒業生への進路追跡調査を本格的に開始。調査対象は毎年約1,200名にのぼり、Webと郵送でアンケートを回収していました。回答形式は選択式に加えて、就職活動の感想や在学中の支援に対する自由記述欄も設けており、入力作業は職員2名で2週間以上を要していたそうです。
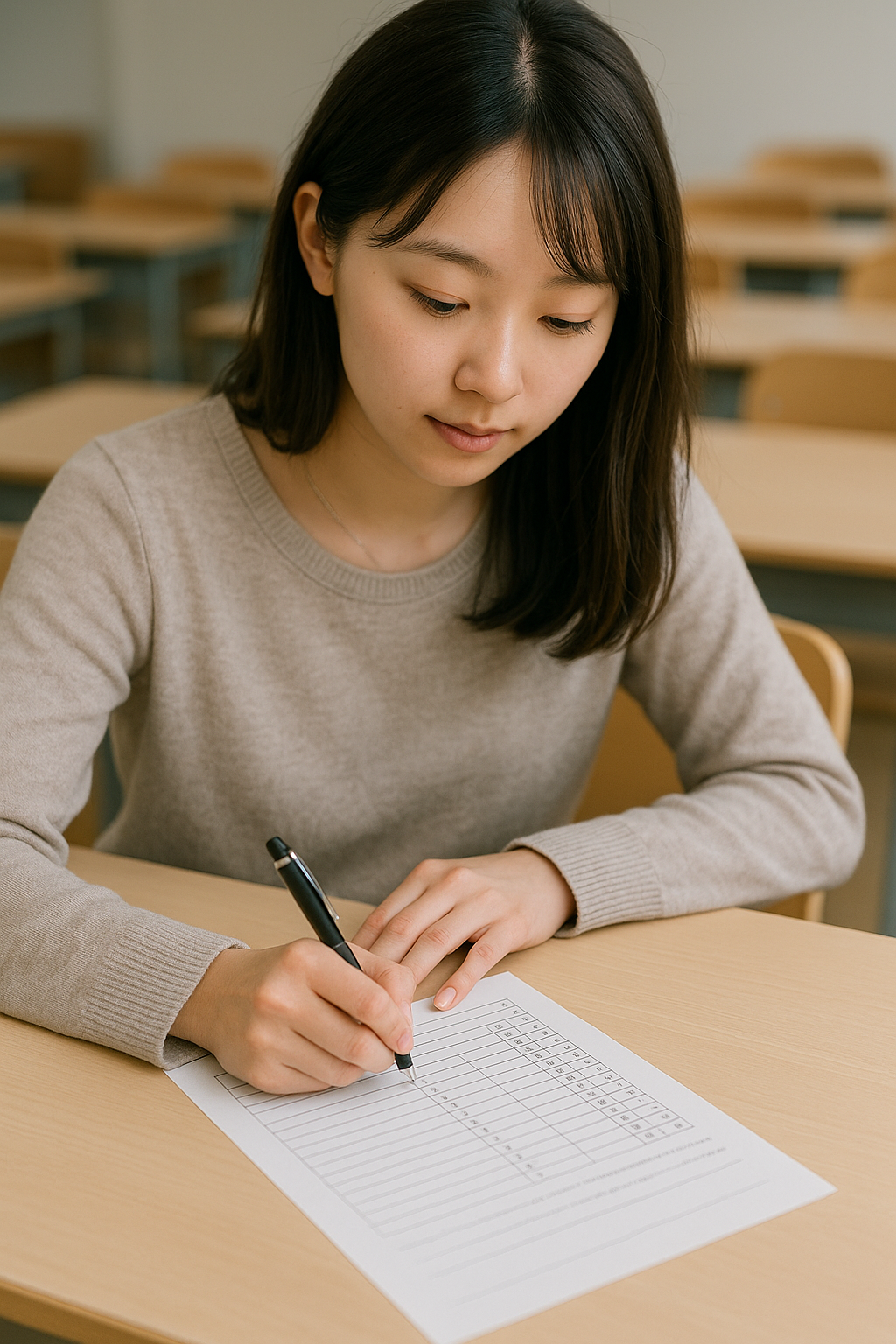
そこで2024年度から入力代行の外注を導入。業者には以下の条件で依頼しました:
-
紙・Web混在のアンケート形式に対応
-
自由記述欄は原文そのままでの入力+カテゴリ分類オプションあり
-
Excel形式+進路分類ごとのフィルタリング可能な構造で納品
結果、入力作業は約4営業日で完了し、職員は集計と報告資料作成に専念できるようになりました。担当者は「自由記述も丁寧に入力されており、内容の把握や引用が非常に楽になった」「次年度以降も継続して外注予定」と高く評価しています。
ケース②:国立大学での「授業評価アンケート」大規模対応
ある地方の国立大学では、全学部の正規授業に対して年2回、授業評価アンケートを実施しており、1回あたりの回答数はおよそ5,000件に達します。設問数は15問程度、うち2問が自由記述。かつては各学部の事務職員がそれぞれ手分けして入力していたものの、学期末の繁忙期と重なって作業が遅延し、報告会資料作成が間に合わないという課題が生じていました。
この問題を受けて、2023年度より入力業務を一括外注。業者とはあらかじめ以下のような条件を合意:
-
記述欄に不適切表現があった場合の処理方針(例:伏せ字化、注記付加)
-
入力ミスの二重チェック体制
-
納品形式のテンプレートを大学とすり合わせた上で作業実施
-
回答内容ごとの集計分類(良い点・改善点など)のタグ付け対応
外注化によって作業期間は約1/3に短縮され、報告資料の作成も前倒しで進められるようになりました。また、記述回答をカテゴリ別に自動分類してもらえたことで、授業改善会議での説明が視覚的にわかりやすくなったという意見も寄せられています。
ケース③:女子短期大学での「入学直後アンケート」の柔軟活用
関西にある女子短期大学では、新入生を対象とした「生活実態アンケート」を入学後すぐに実施しています。調査は紙で配布し、その場で回収。設問は学習習慣、生活リズム、交友関係、金銭面の不安など多岐にわたり、自由記述欄も比較的多い構成でした。
従来は学生支援課の職員が手作業で入力していましたが、年度初めのガイダンス業務と重なり、入力にかける時間が確保できない状態が続いていました。
そこで、外注業者に以下の点を重視して依頼:
-
紙アンケートの原本を送付後、1週間以内に納品
-
自由記述欄の文字起こしと「悩み・支援要望」に関するタグ付け分類
-
ExcelとPDFの2形式での納品(教員との共有用)
結果、調査実施から10日以内に全学部の集計が完了し、新入生支援の初期対応を迅速に開始できたという大きな成果が得られました。特に、孤立や不安を抱える学生の早期発見につながった点が好評で、「福祉的支援や面談に生かせる分析ができた」との声も上がっています。
共通する成功要因と、スムーズな導入のポイント
これらの事例に共通するのは、次の3点です:
-
入力項目の仕様や分類ルールを事前に明確化していること
-
大学内での活用目的に沿った納品形式を選択していること
-
自由記述への対応を含めた精度・スピード重視の業者選定を行っていること
また、スムーズな導入を実現するために重要なのは、見積もり前の段階から業者と情報共有を行い、信頼関係を築くことです。初回の依頼時に「入力ルールのガイドライン」や「過去のアンケート様式」「集計結果のサンプル」などを提示しておくと、業者側の理解も深まり、納品の質が高まります。
次章では、ここまでの内容を総括し、大学にとってアンケート入力外注がどのような戦略的価値を持つかをまとめ、導入を検討する際のポイントを再確認します。
まとめ:教育の質と現場の働き方改革を両立するための外注活用戦略
学生・卒業生を対象としたアンケートは、今や大学における教育改善、キャリア支援、教学マネジメントの基盤を支える欠かせない業務です。とくに2025年度以降は、文部科学省による内部質保証の強化やIR(Institutional Research)推進の流れにより、アンケート結果を迅速かつ的確に分析・活用する力が大学の競争力を左右する時代に突入しています。
しかし、その一方で、実際にアンケートの入力業務を担っている大学職員の多くが、限られた人員・時間・設備の中で、煩雑で膨大な作業を抱え込んでいるのが現実です。業務の属人化や納期遅延、入力ミスのリスクが常態化している大学も少なくありません。
こうした課題を抜本的に解決し、かつ教育の質と職員の働き方を両立させる施策として、アンケート入力業務の外注(入力代行)は非常に有効な手段となり得ます。
アンケート入力の外注は「雑務の委託」ではない
外注というと、「面倒な作業を外に出す」イメージを持たれがちですが、大学におけるアンケート入力の外注は、それ以上の戦略的な業務改革です。
-
迅速なデータ化により、報告書や意思決定が前倒しで進められる
-
精度の高い入力によって、分析結果の信頼性と再利用性が向上する
-
職員が創造的・判断的な業務に注力でき、人材活用の最適化が図れる
これらは単なる業務負担の軽減を超えて、大学全体の「知の循環スピード」を加速させる効果を持っています。
働き方改革の一環としての外注活用
近年、大学事務においても「働き方改革」の波が押し寄せています。学生対応・学内会議・制度改正対応などで日々多忙を極める中、時間外労働の是正やメンタルヘルス対策が求められるようになりました。
そうした中で、アンケート入力のように「重要だが単純作業が多い業務」を信頼できる外部パートナーに委ねることで、職員のワークライフバランス改善にもつながるという側面は見逃せません。とくに年度末や学期末など繁忙期には、外注による作業分散が組織全体の健康維持にも寄与します。
「部分外注」から始めてスモールスタートも可能
外注に不安を抱く大学にとっては、「いきなりすべて外に出す」のではなく、部分的に委託することで試行的に始めるという方法も現実的です。
たとえば:
-
自由記述欄だけを外注して、選択式は内部処理
-
卒業生アンケートだけを外注し、在学生調査は継続実施
-
年間で一番ボリュームの多い調査だけ外注して、年間運用モデルを検証
このような段階的導入により、業者との相性や業務精度を確認しながら、安全かつ効果的に外注を組み込むことが可能です。
専門業者との信頼関係構築が成功のカギ
アンケート入力の外注を成功させるには、大学側と業者側の信頼関係構築と丁寧な事前設計がカギとなります。
-
入力ルールや分類基準を明確に伝える
-
過去のフォーマットや調査票を共有する
-
中間納品やサンプル確認の工程を設ける
-
学内の目的(教学改善/IR分析/報告書作成)を明確に伝える
これらのステップを踏むことで、大学の目的に沿った形で、高品質なデータを迅速に得ることが可能になります。
アンケート入力業務に課題を抱える大学関係者の皆様へ
もし、次のような課題や不安を抱えている場合には、ぜひアンケート入力の外注を一度ご検討ください:
-
回答数が多く、入力作業に手が回らない
-
職員の業務負担が限界で、残業が常態化している
-
入力ミスや記述欄の判断にバラつきが生じている
-
結果の集計・報告が期日に間に合わない
-
調査はしたものの、結果を活用できていない
これらは、すべて「外注によって解決できる可能性が高い課題」です。
▶ アンケート入力外注をご検討の大学ご担当者様へ
私たちB-Outsource.comでは、大学・教育機関向けのアンケート入力代行に豊富な実績があります。
自由記述欄の丁寧な入力、納品形式の柔軟対応、個人情報保護に配慮したセキュアな体制を整えております。
小規模な部分外注から大規模な全学対象の調査まで、ご要望に応じて最適なプランをご提案可能です。
まずはお気軽に、下記のページからご相談ください。
📩 アンケート入力代行サービス|BPO専門のB-Outsource.com
【350社以上への正確な納品実績!パソコン業務・オフィス事務の業務代行を実施!アウトソーシングサービス「ビーアウト」のご紹介】
パソコン・タブレット・コピー機・スキャニング機器などを使った単純なデータ入力・リスト作成・メールDM送信・販促作業・軽作業などを社内スタッフが行うと、御社にのし掛かるコストと時間が無駄になります!
パソコン業務・オフィス軽作業の業務代行サービス「ビ―アウト」の顧客企業は、大手企業から中小企業まで幅広く、東証上場企業様を含む350社以上からのご依頼実績と大量の業務をこなしてきた経験があります。特に、パソコン・タブレット・コピー機・スキャニング機器などでの作業の正確さやスピードでは、クライアント様から大きな信頼を頂いています。また、弊社ではプライバシーマーク(Pマーク)を取得しており、情報データ等の取扱いは慎重に実施しています。
ビーアウトでは、事務作業の確実性やスピード力に比して代行サービスを低価格でご提供しており、これまでご満足頂いてきました。ビーアウトの業務代行サービス内容は、「企業や店舗から委託されるSNS(インスタグラム・ツイッター)の運用代行」「ホームページのSEO対策に関わるコンテンツ作成・ブログ作成」「名刺・文字・アンケート等のデータ化」「契約書や領収書などの書類のスキャニング」「WEBサイトを検索して企業情報の営業リスト作成代行」「企業が持つホームページのブログ作成代行」「メールでのDM送信」「郵送ダイレクトメール(DM)の印刷・封入・発送」など様々です。
もし、御社の社員やスタッフがパソコン・iPad・コピー機・スキャン機器などを使った単純作業を行う場合、その作業に掛かるコストを「時給作業に掛かった時間」だけで計算しているかもしれません。しかし実際には、スタッフを募集・採用・教育する際にかかるコストや労務管理コスト、その他社会保険や賃料などを考えると、少なく見積もってもその1.5倍ほどのコストが会社に掛かっています。
もっと言うと、その単純事務作業の仕上りをチェックし、スタッフのモチベーション維持を図る管理者に掛かる精神的・時間的コストや、そのスタッフがいつ退職するか分からないリスクなど、目に見えないコスト・リスクを考えると、会社が抱える負担は図り知れません。その結果、予算を大きく蝕むことになってしまう単純事務作業は、会社にとって悩みの種だとよく伺います。
その中で、何とか企業様が抱える問題を解消する方法はないかと考え、名刺データ入力・文字データ入力・スキャニング・営業リスト作成・ホームページ記事作成・SNS投稿・オフィス軽作業などの単純作業を低コストで代行する事務アウトソーシングサービス「ビーアウト」を展開しています。弊社にご依頼頂くことで、大量の単純事務作業をアウトソーシング(外注化)でき、しかも「低コスト&スピーディー&正確」に実現できます。
単純なパソコン事務作業やオフィス軽作業の外注代行サービスをお考えなら、ぜひ一度弊社にお問合せ・ご相談ください。
会社概要
