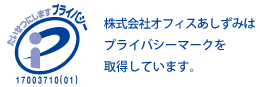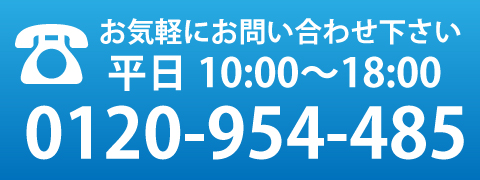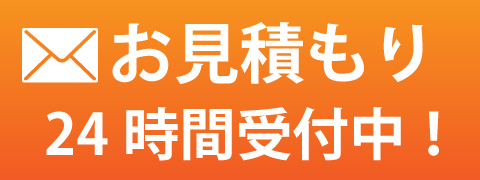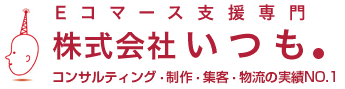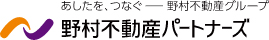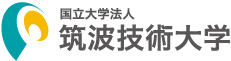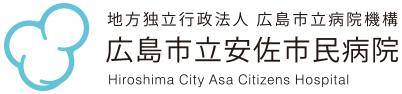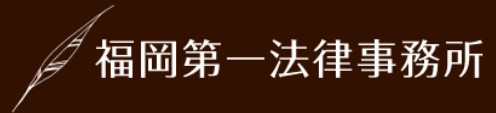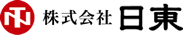目次
商品価格の決め方
商品価格の決め方にはいくつかの方法がありますので、ご紹介します。コスト志向型
コスト志向型の価格の決め方の特徴は、まずはその商品にどれくらいのコストがかかっているかを算出する必要があります。原材料費はもちろん、人件費、輸送費、設備費など様々な角度からコストを計算します。商品原価を算出することができたら、そこに利益を加えます。原価1,000円の商品で利益が30%欲しいのであれば、商品価格は1,300円になります。
需要価格重視型
需要価格重視型の価格設定方法の特徴は、販売したい商品を、消費者がどの程度の価格で入手したいかを考え、価格設定する方法です。この方法を採用するには、販売する商品がどの程度の価格帯で購入されるかを見極める必要があります。子供向けに販売する商品であれば、そこに合わせた価格でなければいけませんし、ブランド品を販売するのであれば、購入するターゲット層がどこになるかも知る必要があるでしょう。競合価格調査型
競合価格調査型の特徴は、同じ商品を販売している競合他社であったり、販売する商品と同じようなジャンルの商品の価格を、まずは調査する必要があります。競合価格調査型の場合、この価格調査の精度が非常に重要になりますので、サンプルとなる競合他社はなるべく多いほうがいいでしょう。 競合他社の価格調査が完了したら、あとは利益を損ねない程度で、かつ競合他社とも近い価格帯での価格を設定します。この時に競合他社よりも高すぎる価格設定にしてしまうと、商品が売れなくなってしまいますし、また安すぎても利益が下がってしまい、商品自体の値崩れの原因となってしまいますので、適正な価格を設定することを心掛けましょう。
価格の見せ方
価格の見せ方にもいくつか方法がありますので、ご紹介します。心理テクニックを利用した価格の見せ方
よく見かける方法ですが、「1,000円」と表示するのと「980円」と表示するのでは見た目の印象が全く違ってきます。桁が変わってくる場合はもちろんですが、「2,000円」の場合よりは「1990円」の方が人は安く感じる傾向があります。また日本では「1,990円」よりも「1,980円」のように「イチキュッパ」が好まれる傾向があります。このように人間の心理を考慮して、価格の見せ方を変えることも重要になります。表示する金額が低くなるようにする
こちらもよく見かける方法ですが、「1日あたり〇〇円」「1回あたり〇〇円」というように、価格の計算式を変えて、表示する価格がより低くなるようにする方法も効果的です。「1ヶ月あたり〇〇円」と大きな金額を表示されるよりも安く感じるでしょう。おとり効果で安く感じさせる
こちらも昔から使われている方法ですが、販売したい商品のすぐ隣に、わざと同じジャンルの高額な商品を並べて表示する方法です。こうすることにより比較対象がうまれ、高額な商品がおとりとなって、販売したい商品を安く感じさせることができるのです。